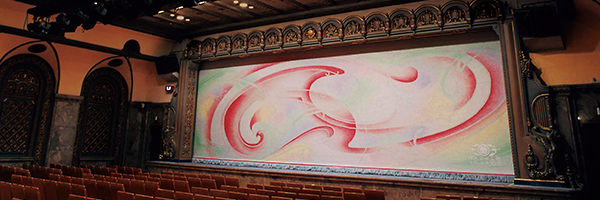三井のスポット
三井文庫
時間の流れから解き放たれ
歴史の息づかいを
今に残す特別な場所
住宅が建ち並ぶ静かな道を歩いていくと、空気が少しずつ湿り気を帯びてくる。緑の多い街並みを抜け、一層木々が生い茂る門が見えると、そこが「三井文庫」の入り口。その様相からは、時間の流れが止まったかのような不思議な気配が漂っている。館に続く道を歩き深閑としたつめたい空気に包まれていると、静謐という言葉の意味を肌から知ることができるようだ。
流れる時間を離れた不思議な静けさの中で

杉並から新宿へと流れる妙正寺川の南、中野区・上高田は閑静な住宅地と寺院の多い街だ。周辺には日照山東光寺や哲学堂公園などがあり、土地が醸す文化的な雰囲気をそこかしこに感じられる。三井文庫に向かって歩を進めると、その荘厳なたたずまいと深い緑が放つ濃密な空気感が相まって、少しずつ時間の進み方が遅くなっていくような感覚がにじみ出す。そして、館内に足を踏み入れるや否や、すべての動きが止まったような静けさが広がっている。ひそやかに息づくのは、数百年の時を超えて受け継がれてきた莫大な史料群。歴史を司る場所だけが持つその雰囲気は、どこかなつかしい。
三井文庫の前身は、明治36年(1903)に設立した三井家編纂室だ。もともとは三井家の修史事業を目的として、日本橋駿河町の三井本館内で事業に当たっていた。三上参次(東京帝国大学教授)、横井時冬(東京高等商業学校教授)らを顧問に迎え、東京・京都・大阪・松阪の各地に散在していた三井家史料を収集整理するとともに、「三井家史」の編纂も進行。明治42年(1909)には、三井11家の当主ごとに歴史をまとめた84冊に及ぶ『稿本三井家史料』が完成。その後、『三井家記録文書目録』5冊も作り上げ、三井の歴史を一手にまとめる礎となった。

團琢磨の辞令

三井銀行創立願書
激動の時代をくぐり抜けてきた足跡
大正7年(1918)、拠点移転とともに三井文庫へと改称。三井大元方史、呉服事業史、両替事業史などの編纂も進められたが、いずれの所蔵史料も世間に公開されることはなかった。やがて第二次世界大戦が激化し、一部の史料は焼失したものの、多くは神奈川県や山梨県で戦火を免れる。しかし、終戦とともにGHQの指令により三井本社は解散。三井文庫も必然的に活動停止を余儀なくされる。敷地と建物は文部省に売却され、所蔵史料も文部省史料館に寄託が決定。三井家への史料返還が叶い、財団法人として改めて三井文庫が再建するまでには、20年の時を待たなくてはならなかった。
現在の地で再び三井文庫が開かれたのは、昭和40年(1965)5月のことだ。その際、従来は門外不出であった三井家文書が公開されることとなったが、背景には近世史・近現代史の実証的研究の進展に寄与するという役割があった。事実、三井文庫本館の所蔵史料は、17世紀半ば以降の三井家古文書類と、明治以降の三井系企業経営資料を中心として10万点にも及ぶ。近世としては、三井家の営業統括機関であった大元方の決算簿「大元方勘定目録」や、越後屋呉服店、三井両替店の経営資料を中心に、各店の勘定目録や補助的帳簿などの決算書類が所蔵されている。また、三井合名会社から三井本社へと変遷をたどり、財閥解体指令を受けるまでの規則類、帳簿、決算表など、歴史的にも価値の高い貴重な史料が揃う。

駿河町越後屋正月風景図(作者不詳)

大元方勘定目録

三井両替店の大福帳
使命は、変わらぬ姿で歴史を守り続けること
三井家の歴史を物語る史料を守り、今に伝える三井文庫。変質させずに史実を伝えるという使命が故に、ここは時の止まったような空気をまとっているのかもしれない。都内にありながらも、時代に流されることなく独特な存在感を保つ上高田の街に、その姿はよく似合う。今が昔と呼ばれるようになったときにも、訪れた者に同じ表情を見せてくれるにちがいない。
三井文庫略年表
| 明治36年 (1903) | 日本橋駿河町・三井本館内に、「三井家編纂室」創立 |
|---|---|
| 明治42年 (1909) | 『稿本三井家史料』(84冊)完成 |
| 大正5年(1916) | 『三井家記録文書目録』(5冊)完成 |
| 大正7年(1918) | 三井家編纂室は荏原郡・戸越に移転し、「三井文庫」に改称 |
| 昭和20年(1945) | 空襲で事務所全焼、土蔵にも延焼 |
| 昭和24年(1949) | 文部省に三井文庫の土地・建物を売却し、収蔵品を寄託する |
| 昭和39年(1964) | 文部省と三井家との間で、三井家文書返還の覚書を交わす |
| 昭和40年(1965) | 中野区上高田に「財団法人三井文庫」創立 |
| 昭和60年(1985) | 「三井文庫別館」が竣工。美術品の一般公開開始 |
| 平成13年(2001) | 約30年に及ぶ『三井事業史』編纂が完了する |
| 平成17年(2005) | 三井文庫別館を日本橋に移転し、「三井記念美術館」開設 |
| 平成22年 (2010) | 内閣府より公益財団法人の認定を受ける |

創立当初の旧三井文庫
INFORMATION
三井文庫
[所在地] 東京都中野区上高田5-16-1
[URL] http://www.mitsui-bunko.or.jp/
[開館時間] 午前10時~午後4時30分
[休館日] 土曜・日曜・祝日・年末年始(12月28日~1月5日)、毎月末日(土・日曜に当たる時はその翌日)、三井文庫創立記念日(5月14日)、その他あらかじめ公示する臨時休館日(庫内燻蒸など)
[利用条件]
原則として20歳以上の研究者に限ります。
初めての利用者は、所属機関長・指導教官など適当な紹介者を要します。
一部の資料は公開準備中。寄託史料については別途利用条件が定められています。
詳しくは、三井文庫までお問い合わせください。
※掲載の資料はすべて公益財団法人 三井文庫所蔵。
※上記の内容は2011年10月15日時点の情報です。
出典:三井グループ・コミュニケーション誌『MITSUI Field』vol.12|2011 Autumn より